1.処暑(しょしょ)とは?(2025年8月23日~9月6日)
「処暑」の「処」は、‟とどまる”という意味を持ち、「暑さが収まり始める頃」を指します。
暦の上では夏の終わりを告げる時期で、少しずつ秋の気配が感じれるようになります。
とはいえ、実際の気温は依然として高く、厳しい残暑が続く地域も多いです。
特に近年では気候変動の影響で、湿気と残暑が重なり、体調を崩いやすい時期となっています。
日本特有の高温多湿の環境では、湿気が体に溜まりやすく、体調管理の重要性がさらに高まります。
この時期をどう過ごすかによって、夏の疲れを引きずるか、快適に秋を迎えられるかが大きく変わってきます。
2.処暑に起こりやすい体の変化
処暑の頃は、夏の間に溜まった「熱」や「湿」が体内に残り、次のような不調を引き起こすことがあります。
①疲れやすい・体がだるい
高温多湿により体力が奪われやすく、汗とともにミネラルも流出します。
その結果、だるさや疲労感を感じやすくなります。

②食欲不振・胃腸の不調
冷房や冷たい飲食の摂り過ぎによる内臓の冷えが、胃腸の働きを低下させます。
食欲がわかない、胃もたれ、下痢や便秘などの不調が出やすくなります。
③むくみ・頭の重さ
体内の水分代謝が滞ることで「湿邪(しつじゃ)」が溜まり、手足のむくみや頭重感、関節のこわばりなどが現れます。
これは、水の巡りが悪くなっているサインです。
④寝つきが悪い・睡眠が浅い
暑さ・湿気・冷房による冷えなどの影響で自律神経のバランスが乱れ、夜になってもリラックスできず、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりすることもあります。
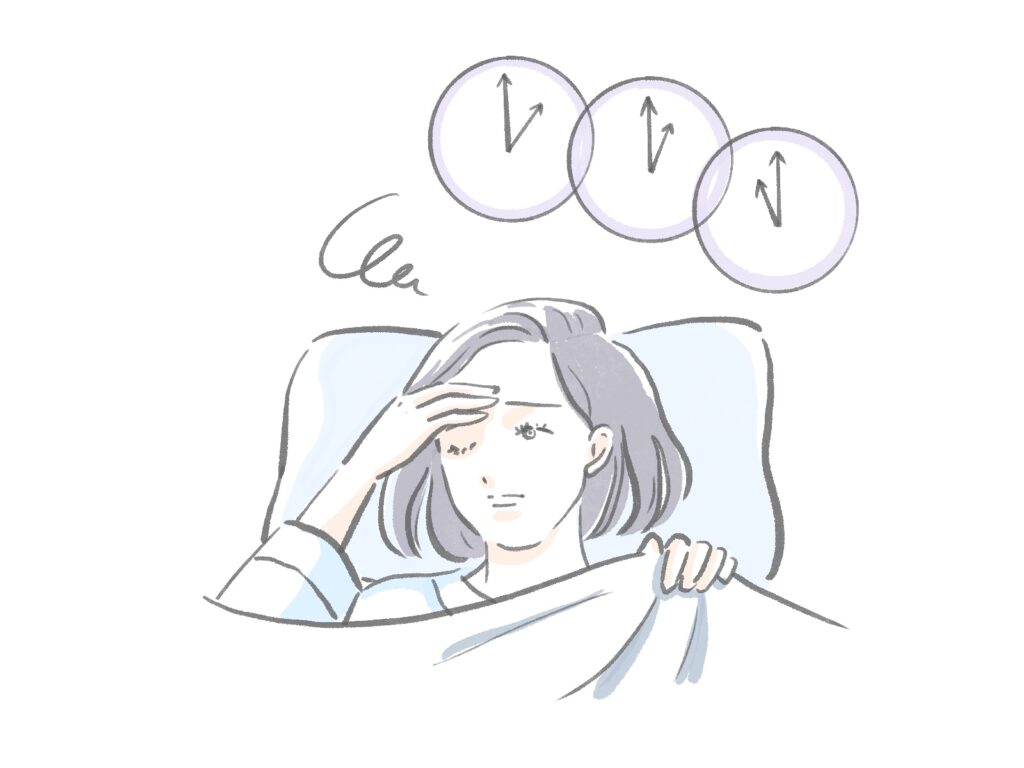
⑤気分の浮き沈み・やる気が出ない
だるさや睡眠不足が続くと、心も疲れてしまい、気分の落ち込みや無気力に繋がります。
湿邪は「気」の巡りを妨げるため、精神面にも影響を及ぼします。
⑥夏バテ・残暑疲れ
夏の疲れが回復しないまま残暑が続くことで、いわゆる「夏バテ」「冷えバテ」の状態になってしまいます。
そのままにしておくと、秋口の体調不良に繋がりやすくなります。
♦不調の原因「湿邪(しつじゃ)」
東洋医学では、夏から秋にかけての体調不良の多くを「湿邪(しつじゃ)」の影響と考えます。
湿邪は、体に溜まった湿気が巡りを妨げ、胃腸の働きや気の流れを乱すものです。
特にこの時期は、以下のような湿が重なりやすく、不調を感じやすくなります。
- 外湿:外からの湿気(高湿度の空気)
- 内湿:体内に溜まった余分な水分
- 冷湿:冷たい飲食や冷房による冷えと湿の組み合わせ
これらが重なると自律神経が乱れ、夏バテ、冷えバテなど、さまざまな不調を引き起こすのです。
3.処暑の養生ポイント
キーワードは「整える・巡らせる・温める」
処暑の時期は、夏の疲れを癒し、秋を元気に迎えるための大切な準備期間です。
①胃腸を労わる
冷たいものの摂り過ぎを避け、胃腸を温める食事を心がけましょう。
特に、朝食に温かい汁物やおかゆなどを取り入れると、内側から体が温まり、体の巡りが整いやすくなります。
良く噛んでゆっくり食べることも大切です。
②体内の「湿」を溜め込まない
適度に汗をかくことで、体内の余分な湿気を排出することができます。
軽い運動や入浴など、無理のない範囲で汗をかく時間を取りましょう。
また、利尿作用のある食事やハーブティー(コーンシルク、レモングラスなど)もおすすめです。

③「気」と「血」の巡りを良くする
処暑以降は、東洋医学で「養肺(ようはい)」の時期とされています。
ストレッチや腹式呼吸、ヨガなどで呼吸を整え、気と血の巡りを促しましょう。
④秋への準備を始める
朝晩の気温が下がり始める季節。
薄手の羽織や靴下、腹巻などで冷えを防ぎましょう。
また、肌や喉の乾燥対策も少しずつ始めておくと安心です。
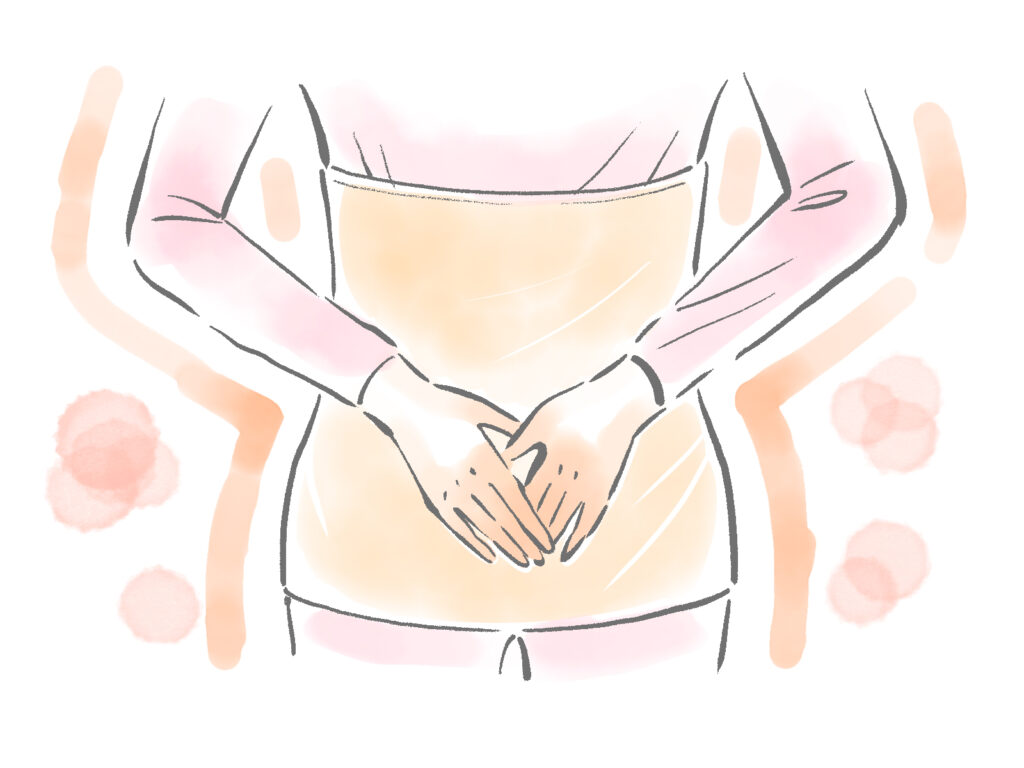
4.この時期におすすめ食材&生活習慣
①おすすめ食材(胃腸を元気に・水分代謝を助ける)
- 冬瓜(とうがん):体の熱を冷まし、余分な水分を排出します。スープや煮物に。
- きゅうり・なす:水分が豊富で体の熱と湿を取ります。冷えやすい人は、加熱調理がおすすめです。
- 生姜・ねぎ:体の内側から温め、冷えた胃腸をサポートします。
- 豆類(小豆・黒豆など):利尿作用で水分代謝を促進します。
- 梨・ぶどう:水分とビタミン補給にピッタリな旬の果物です。
②おすすめ生活習慣
- 適度な運動:ウォーキングやストレッチで、気・血・水の巡りを改善。
- ぬるめのお風呂に浸かる:38~40℃程度のお湯にゆったり浸かってリラックス&発汗。
- 冷房の見直し:室温設定は控えめに、外気との温度差に注意。
- 就寝時の冷え対策:お腹や足元をひやさないよう、腹巻やレッグウォーマーなどを活用。
- 呼吸を整える:深い呼吸で自律神経を整える(腹式呼吸・瞑想など)。

5.おわりに
処暑は、暦の上では夏の終わりを告げる時期ですが、実際の気候はまだまだ油断できません。
夏に溜まった「熱」や「湿」を上手にリセットし、体と心を整えることで、次の季節を元気に迎える準備が整います。
この時期は、「整える・巡らせる・温める」を意識した養生を心がけることが大切です。
無理をせず、自然の流れに寄り添いながら、日々の食事や生活習慣に少しだけ気を配ってみましょう。
季節の移ろいを感じながら、健やかで穏やかな秋を迎えられますように。
ご予約について
完全予約制となっております。
ご予約は店舗へのお電話、またはご予約受付にて承っております。
お問い合わせメールの場合、返信にお時間をいただく場合がございます。
お急ぎの場合はお電話がおすすめです。
ご予約受付
ご相談について
漢方相談では、今のお体の状態や気になる症状について、丁寧にお話をお伺いします。
落ち着いた相談スペースで、リラックスしてご相談いただけますので、初めての方もご安心ください。
体質やお悩みに合わせて、ぴったりの漢方薬をご提案いたします。
ご相談時間はお一人30分くらいです。
松山漢方相談薬局HP
店舗情報
松山漢方相談薬局 横浜桜木町店
- 営業時間:10:00~20:00
- 定休日:第2木曜日
- TEL:045-341-4823
- 〒231-0063
神奈川県横浜市中区花咲町1丁目19-3
セルアージュ横濱桜木町ヴァルール101号室
松山漢方相談薬局 鶴見店
- 営業時間:10:00〜20:00
- 定休日:第2木曜日
- TEL:045-718-6801
- 住所:〒230-0062
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2-2
鶴見フーガII 3階

















