1.大暑とは(2025年7月22日~8月6日)
「大暑(たいしょ)」は二十四節気の一つで、2025年は7月22日から8月6日(立秋の前日)までがその期間にあたります。
一年の中でも特に暑さが厳しく、湿度も高くなるこの時期は、体力を消耗しやすく、心身に大きな負担がかかります。
熱中症や夏バテ、食欲不振、睡眠の質の低下など、さまざまな不調が起こりやすく、特に高齢者や小さな子ども、体力や免疫力が落ちている人は注意が必要です。
そんな過酷な季節を元気に乗り切るためには、自然のリズムに寄り添いながら日々の養生を意識することが大切です。
ここでは、大暑の時期に起こりやすい体の変化と、その対処法をご紹介します。

2.大暑の時期に体が受ける影響
①汗による「気」と「津液(しんえき)」の消耗
東洋医学では、人間の体内には「気(生命エネルギー)」と「津液(体を潤す体内の水分)」が巡っており、これらのバランスが健康の基本と考えられています。
特に夏の暑さや激しい運動などで汗を大量にかくと、「気」と「水分」が同時に消耗されやすくなります。
「気」が不足すると、だるさ、無気力感、疲労感などの不調が出やすくなります。
「津液(体を潤す体内の水分)」が不足すると、喉の渇き、口や肌の乾燥、便秘、尿の減少など、体の潤いが失われているサインが現れます。
②食欲不振と胃腸の機能低下
暑さで体がだるくなると、自然と食欲が落ちてしまいます。
加えて、冷たい飲み物やアイスなどを摂り過ぎると、胃腸の働きが鈍くなり、消化不良や下痢、倦怠感などを招くことがあります。
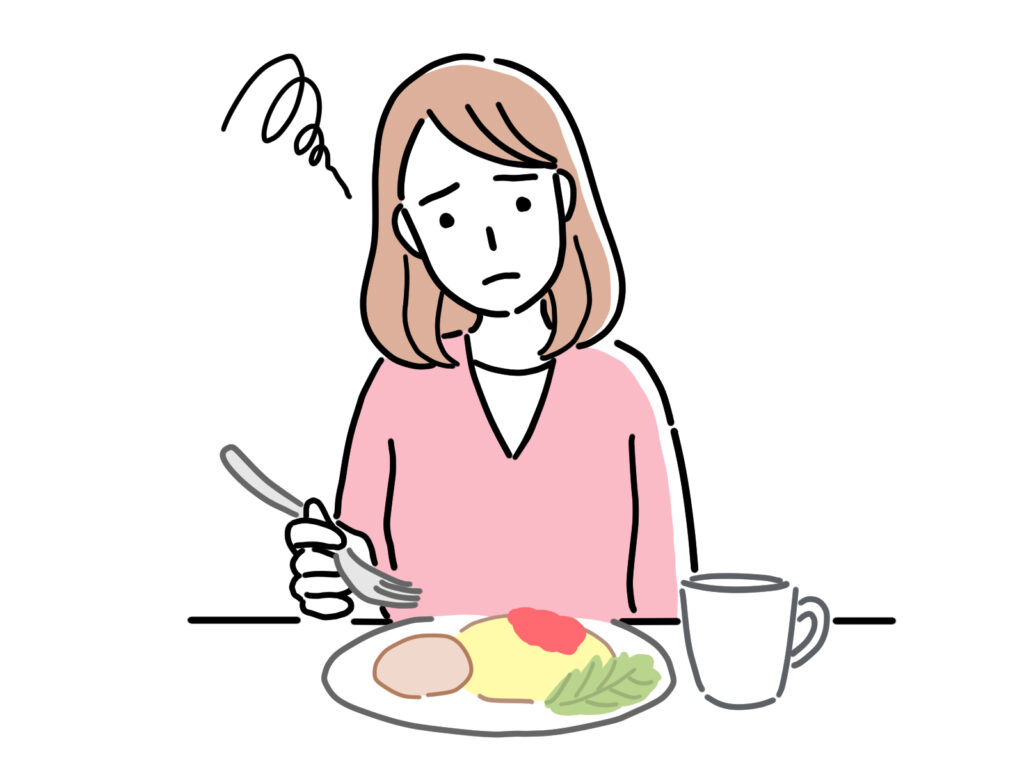
③睡眠の質の低下
夜になっても気温が下がらず、寝苦しさから深い睡眠がとれずに疲れが蓄積しやすくなります。睡眠不足は、自律神経の乱れ、免疫力の低下や体調不良に繋がります。
④高齢者や子どもは特に注意
高齢者は体温調節機能が低下しており、暑さや喉の渇きに気づきにくく、脱水症や熱中症のリスクが高まります。
また、子どもは体温調節機能が未熟で環境の影響を受けやすいため、こまめな観察とケアが欠かせません。
このように、体への負担が大きくなる大暑の時期には、意識的に「養生=体と心をいたわる生活」を心がけることが、健康維持の鍵となります。
3.体を守る「大暑の養生」実践法
①食養生
- 気を補い、胃腸を守る食材:お粥、冬瓜、かぼちゃ、豆腐、鶏むね肉・ささみ、白身魚 など
→煮る・蒸すなどの加熱調理で、さらに消化が良くなります。特に、温かいお粥やスープは、胃腸にやさしく、疲れた体に染み渡ります。 - 体の熱を冷ます夏野菜:きゅうり、トマト、なす、ゴーヤ、すいか など
→これらの野菜には「清熱作用」があり、体の内側から熱を冷ます働きがあります。生のまま食べることで冷却効果を得られますが、胃腸が弱い方は軽く加熱することで負担を和らげることができます。 - 香味野菜をプラス:しょうが、しそ、みょうが、ねぎ など
→消化を助け、食欲を高めてくれます。また、適度に体を温める作用もあります。 - 温かい汁ものを一品加える:冷たい物ばかりだと胃腸が冷えて、消化機能が低下してしまいます。味噌汁やスープなど温かい物を意識的に取り入れましょう。

②水分補給
- 喉の渇きを感じる前に:高齢者や子どもは喉の渇きを感じにくいため、水分不足に気づかないことがあります。そのため、時間を決めてこまめに摂ることが効果的です。
- 塩分やミネラルをしっかり補う:汗とともに、体に必要な塩分やミネラルも失われます。麦茶、梅干し、塩昆布、みそ汁など、自然なかたちで補うのがおすすめです。
スポーツドリンクに頼りすぎず、日常の食事や飲み物の中でバランスよく取り入れていきましょう。
③生活習慣の見直し
- 朝の時間を活用:日中に比べて気温が比較的落ち着いている朝のうちに、散歩や買い物などを済ませておくと、体への負担を軽減できます。
しかし、最近は早朝でも蒸し暑さが厳しい日もあります。天候や体調に合わせて、無理のないかたちで朝の時間を過ごしましょう。 - 昼寝を取り入れる:15~20分ほどの短い昼寝は、自律神経を整えるのに効果的です。
長すぎると夜の睡眠に影響することもあるため、時間には注意しましょう。 - ぬるめのお風呂でリラックス:38~40℃のぬるま湯に10〜15分ほどゆっくり浸かると、心身の緊張がほぐれ、汗をかきやすくなり、深い眠りにもつながります。
暑い日こそ、シャワーだけで済ませず、湯船にゆったり浸かる時間を大切にしましょう。 - ゆとりあるスケジュール管理:無理をせず、自分のペースを大切にしましょう。予定に余裕を持たせることで、心にもゆとりが生まれ、疲れを和らげます。
④暑さ対策の徹底
- エアコンを上手に使う:室温は28℃前後を目安に、無理のない範囲で快適に過ごしましょう。扇風機やサーキュレータ―と併用すると、冷気が循環しやすくなります。
冷やし過ぎると体調を崩すこともあるので、体に直接冷風が当たらないように気をつけてください。 - 衣服で調節:通気性や吸湿性の高い綿や麻などの天然素材を選ぶと、汗をしっかり吸収・発散してくれます。
外出時は、帽子や日傘で直射日光を防ぎ、できるだけ日陰を歩くように意識しましょう。
保冷材や冷感タオルなども、首元にあてると体感温度が下がりやすくなります。

4.心も「涼しく」整える
暑さが続くと、体だけでなく心も知らず知らずのうちに疲れてしまいます。
イライラしやすかったり、気力が湧かなくなることも。
そんな時は、無理に頑張るよりも、自分の心にそっと寄り添うことが大切です。
①自分の「気持ち」に気づく習慣を
イライラ、不安、だるさなど、ネガティブな感情が湧いてくるのは、心が疲れているサイン。
「感じてはいけない」と否定するのではなく、「今、自分は疲れているんだなぁ」「こういう時もある」と、優しく受け止めましょう。
日記やメモに書き出すだけでも、気持ちが整理され、落ち着いてきます。
②五感で「涼」を取り入れる
五感を通じて「涼しさ」や「心地よさ」を感じることは、自律神経のバランスを整え、心を穏やかに保つ助けになります。
- 視覚:青、白、透明感のある色を使ったインテリアや食器を取り入れてみましょう。視界に入るだけで、涼やかな気分になれます。
- 聴覚:風鈴や水の流れる音、自然のささやきが感じられる音楽などがおすすめです。耳から涼しさを取り入れて、心地よくリラックスしましょう。
- 嗅覚:ミントや柑橘系、ラベンダーなど、清涼感やリラックス感のある香りを取り入れてみましょう。香りは気分をリセットするのにも効果的です。
- 触覚:麻や竹素材の衣類・寝具は、さらりとした肌触りで、体にも心にも心地よさを届けてくれます。
- 味覚:梅干しや柑橘類の酸味、ミントの清涼感を感じられる飲み物や料理を取り入れてみましょう。さっぱりとした味わいが体の熱を和らげ、爽やかな気分にしてくれます。

5.さいごに
大暑は、「体調管理の分かれ道」となる時期です。
夏を過ごす中で、ちょっとした無理や油断が体調不良の原因になることもあります。
だからこそ、この時期にしっかりと養生を意識することで、秋以降の体調も整いやすくなります。
養生とは、特別なことをするのではなく、毎日の暮らしの中で自分をいたわる小さな積み重ねです。
たとえば、冷たいものを摂り過ぎない、こまめに水分をとる、いつもより少し早めに寝る——
このような工夫が、体と心にゆとりをもたらしてくれます。
大切なのは、自分の体と心に耳を傾けながら、無理のないペースでできることを少しずつ取り入れていくこと。
それが、元気に夏を乗り切るための近道です。
「暑いからこそ、ゆったり、やさしく、ていねいに」
自然のリズムに寄り添いながら、この夏を心地よく過ごしましょう。

ご予約について
完全予約制となっております。
ご予約は店舗へのお電話、またはご予約受付にて承っております。
お問い合わせメールの場合、返信にお時間をいただく場合がございます。
お急ぎの場合はお電話がおすすめです。
ご予約受付
ご相談について
漢方相談では、今のお体の状態や気になる症状について、丁寧にお話をお伺いします。
落ち着いた相談スペースで、リラックスしてご相談いただけますので、初めての方もご安心ください。
体質やお悩みに合わせて、ぴったりの漢方薬をご提案いたします。
ご相談時間はお一人30分くらいです。
松山漢方相談薬局HP
店舗情報
松山漢方相談薬局 横浜桜木町店
- 営業時間:10:00~20:00
- 定休日:第2木曜日
- TEL:045-341-4823
- 〒231-0063
神奈川県横浜市中区花咲町1丁目19-3
セルアージュ横濱桜木町ヴァルール101号室
松山漢方相談薬局 鶴見店
- 営業時間:10:00〜20:00
- 定休日:第2木曜日
- TEL:045-718-6801
- 住所:〒230-0062
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2-2
鶴見フーガII 3階

















