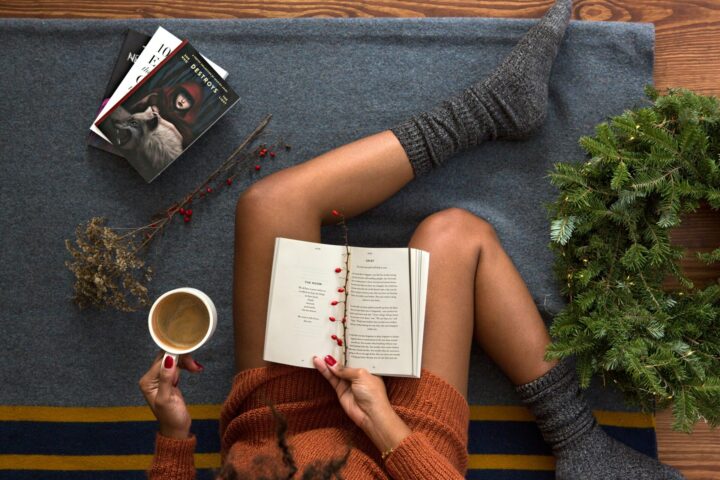8月もそろそろ終盤ですが、暑さにこたえる日が続きますね。
しかし、こんな暑さでもからだの冷えに悩まされることが珍しくありません。
これから秋、冬にかけて気温も下がってくると本格的に冷えを感じる人も増えてくるかと思います。
現代は食品や料理に「減塩」というワードがよく飛び交っています。
血圧が高い日本人が増え、「塩分は血圧を上げる」「塩は悪」というイメージがこびりついているのが現状だと感じます。
しかし、東洋医学では塩を絶対的な悪だとは考えていません。
むしろ、からだを冷やしている原因のひとつに減塩のしすぎが考えられます。
今回は冷えと塩分摂取について、からだの組成から東洋医学の考えを踏まえてお話していきます。
知ってる?からだの組成

細胞のはなし
からだを構成する一番小さい単位が細胞です。
からだの外側と直接接している細胞は皮膚と粘膜のみです。
それ以外のからだの内側の細胞はあらゆる変化に敏感に反応します。
そのため、我々人間にはからだの中の環境を一定に保つ「恒常性(ホメオスタシス)」という機能が備わっています。
水分のはなし
一般的に、成人男性の体重の約60%が水分だといわれています。(女性や高齢者は約50%、乳児は約70%)
そしてそのうちの2/3が細胞の中に(=細胞内液)、残り1/3が細胞の外に(=細胞外液)存在します。
細胞は膜で覆われており、それが細胞の外との仕切りとなっています。
細胞の中と外といってもイメージしづらいかもしれませんね。
この水分は血液など、からだの液体すべてを指しています。血液は血管を通るものなので、細胞の外に存在するものです。また、細胞と細胞の間に存在する液体も細胞外液といいます。
場所が違えば、役割もそれぞれあります。
細胞の中ではエネルギー産生やタンパク合成などの代謝に関わります。
そして細胞の外側では循環血液量の維持や栄養素・酸素の運搬、老廃物の排出などを行います。
細胞の中の水分は外の2倍あることには意味があります。

水は移動する?!
循環血液量(体重の約8%)が減ってくると、からだは危機を感じます。
このとき、水が細胞の中→外へ移動して、不足する外の水分を補うリザーバーのような役割もあるのです。
このように、体内では濃度を一定に保つために【水をひっぱる力】が働きます。
これを「浸透圧」といいます。昔理科の授業で聞いたことがある記憶がある人もいるでしょう。
細胞の中にも外にも、「電解質」と呼ばれるミネラルが水と存在しています。
主に、細胞の中にはカリウムイオン、細胞の外にはナトリウムイオンが多く存在します。
体液は0.9%食塩水の濃度が正常であり、これから外れてくると水が濃度の濃いところを薄めようと動きます。
突然ですが、ナメクジに塩をかけたことはありますか?🧂😣
結論からいうと、ナメクジは小さくなってしまいます。
これも浸透圧によるもので、ナメクジのからだの中の水分が、塩(ナトリウム)が多い外に出てきてしまうためナメクジは小さく干からびたような状態になるのです。
ここからは、人間のからだで考えてみましょう。
むくみはどこから?
特に女性のお悩みに多いのが「むくみ」です。
これは水分代謝の異常で起こるトラブルです。
むくみは、細胞の外の水分が増えることが原因で生じます。
しょっぱいものを食べたらむくみやすいんだよな~、なんて思い当たる人もいるのではないでしょうか。
塩分(ナトリウム)は細胞の外にとどまるため、細胞の外の濃度が上がります。そうすると細胞の中から水が移動し薄めようと細胞の外の水分が増えるため、むくみにつながります。
そのため、むくみの原因はただ単に水をとりすぎているわけではなく、塩分過多による細胞内外のバランスの崩れからきているといえます。

東洋医学で考える「水」のトラブル
東洋医学では、からだを構成する要素として〈気・血・水(津液)〉のバランスを重要視します。
水と津液のちがいって?
水:飲食物に含まれるもの
津液:水がからだの中で変化したもの(汗、涙、唾液、胃液、関節の液体、ホルモンなど)の総称
さらに津液が変化したものを<気・血・水>の「血」と考えます。
ちなみに津液は、正常な体液のことをいいます。
津液になれなかったもの(過剰な水、代謝異常などが原因)は、東洋医学では痰飲(たんいん)と呼ばれます。また、この異常な水分が悪さをすることから「水毒(すいどく)」と呼ぶこともあります。
日本の気候が与える細胞への影響
日本は海に囲まれており、多湿な環境です。
これは、湿気により細胞の外の水分が多くなりやすい状態だということです。
つまり、細胞の中が濃度の濃い状態となるため水をひっぱり、細胞の中の水分が増えやすくなります。
細胞の中がブヨブヨになっている状態をイメージしてください。
この状態で減塩をするとどうでしょう?
細胞の外に必要なナトリウムが補給されないと、ますます細胞のブヨブヨ化が進行しやすくなります。
東洋医学では細胞の中も外も区別せず正常な体液を「津液」と呼びますが、細胞がブヨブヨになってしまった状態は異常な体液の集まりだと考え、水毒といいます。
水毒は停滞し気血の流れを妨げます。
また、重力の影響を受けて特に下半身に停滞しやすい特徴があり、足腰の冷えにもつながりやすいです。
つまり、過度な減塩が冷えを招く恐れがあるということです。
塩と腎の関係
腎のはたらき

腎には大きく3つの働きがあります。
・「腎は水液をつかさどる」・・・水分代謝を担う。必要な水は肺へ、不要な水は膀胱へ。
・「腎は納気をつかさどる」・・・肺で吸い込んだ空気を取り込むのが腎の役割。取り込めなくなると新たに吸えなくなる。
・「腎は精を貯蔵する」・・・成長や発育、生殖機能に必要な精(生命の根源)を蓄える。
腎と塩味
腎は塩味(鹹(かん))と深いかかわりがあります。
東洋医学において、「塩味」には凝集作用があり漬物をイメージすると塩分が強いと野菜もぎゅっと引き締まります。
わたしたちの細胞も適度な締まりが必要です。
この塩味が水分保持にも関わります。
腎では体内の水分調節を行い、血圧にも関与します。
また、東洋医学で大切な考え方である陰陽論(物事を2つに分ける)を食事に当てはめると、
💧陰:野菜や果物(植物性のものに多い)、砂糖、アルコールなど
🔥陽:肉や卵(動物性のものに多い)、塩
のように、塩は陽(からだをあたためるもの)に分類されます。
また、現代では健康には減塩や無塩が推奨されていますが、東洋医学ではよい塩味は腎を養うと考えます。
精製された塩ではなくて、ミネラルをたっぷり含んだ天然の塩が「よい」塩を指します。
いくらよい塩でも、とりすぎは逆に腎を傷めてしまいますし、前述したむくみの原因にもなります。
塩に限らず何事も過ぎるのはよくありませんから適度に食べるようにしましょう。

※ご持病や体質によっては塩分摂取が制限されるケースがありますので、その場合は指導や治療方針に従うようにしてください。
さいごに
「冷えは万病のもと」とも言われます。
体温の低下は免疫力にも影響を及ぼしかねません。
冷えでお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
松山漢方相談薬局では、「漢方薬」「生薬」「栄養素」を用いて
おひとりおひとりの身体にあった方法をプランニングし、
オーダーメイド治療をすることで健康をサポートいたします💡
ご予約について
完全予約制となっております。
ご予約は店舗へのお電話、またはご予約受付にて承っております。
お問い合わせメールの場合、返信にお時間をいただく場合がございます。
お急ぎの場合はお電話がおすすめです。
ご予約受付
ご相談について
漢方相談では、今のお体の状態や気になる症状について、丁寧にお話をお伺いします。
落ち着いた相談スペースで、リラックスしてご相談いただけますので、初めての方もご安心ください。
体質やお悩みに合わせて、ぴったりの漢方薬をご提案いたします。
ご相談時間はお一人30分くらいです。
松山漢方相談薬局HP
店舗情報
松山漢方相談薬局 横浜桜木町店
- 営業時間:10:00~20:00
- 定休日:第2木曜日
- TEL:045-341-4823
- 〒231-0063
神奈川県横浜市中区花咲町1丁目19-3
セルアージュ横濱桜木町ヴァルール101号室
松山漢方相談薬局 鶴見店
- 営業時間:10:00〜20:00
- 定休日:第2木曜日
- TEL:045-718-6801
- 住所:〒230-0062
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2-2
鶴見フーガII 3階