1.寒露とは?(2025年10月8日~10月22日)
「寒露(かんろ)」は、文字通り「寒い露」を意味し、秋が深まり、草木に降りる露がひんやりと冷たく感じられる頃を表しています。
日中は、まだ日差しに温かさが残るものの、朝の冷たい空気や夜に吹く風から、季節の変化を実感する方も多いのではないでしょうか。
鳥たちは渡りの準備を始め、人々の暮らしの中でも、少しずつ冬支度が意識されるようになります。
東洋医学では、「陽(あたたかさ)」の気が次第に弱まり、「陰(冷たさ・静けさ)」の気が強まってくると考えられています。
外からの冷えや乾燥に備えて、体の内側から‟温める力"と‟潤す力"の両方を整えることが大切になってきます。

2.寒露に起こりやすい体と心の変化
冷えや乾燥が強まる寒露の季節は、心と体にさまざまな変化が起こりやすくなります。
こんな不調、ありませんか?
- 朝晩の冷え込みで、手足の冷え・肩こり・関節のこわばり
- 空気が乾いて喉がイガイガ、鼻や肌がカサカサ
- なんとなくだるい、疲れやすい
- 食欲が安定しない、胃腸の調子が気になる
- 風邪を引きやすい、喉が痛い、咳が出る など
東洋医学では、この時期に影響を受けやすいのは「肺」と「腎」と考えられています。
- 肺は乾燥に弱く、喉・鼻・皮膚と深い関係があります。
- 腎は、体を内側から温める‟陽気”の働きを担い、冷えと関りが深い臓器です。
この2つのバランスが崩れると、「乾燥」と「冷え」のダメージがダブルでやってきます。
だからこそ、寒露の養生では【温める・潤す】ことのバランスが大切なのです。

3.寒露の養生ポイント
①万病のもと「冷え」を防ぐ、ぬくもりの工夫
寒さが深まるこの時期は、体の内側まで冷えが届きやすくなります。
冷えは風邪を招くだけでなく、生理不順・腰痛・便秘など、日々の体調にも影響を与えることがあります。
冷やさない生活習慣を意識しましょう!
- 薄手のインナー+羽織物で調節をする
- 足元・お腹・腰回りをしっかり保温(レッグウォーマー、腹巻がおすすめ)
- 生ものや冷たい飲み物は控え、温かいものを中心に摂る
「体温が1度下がると免疫力は30%低下する」とも言われます。
冷え対策は、風邪予防や免疫力アップにもつながります。
②からだの潤いを守り、秋の乾燥に備える
空気の乾燥が進むと、喉・鼻・肌などに不調が出やすくなります。
- 喉のイガイガ
- 空咳
- 目のかすみ・乾燥
- 肌のカサつき・かゆみ
これらは、「肺」が乾いているサインかもしれません。
東洋医学では、肺は潤いを好み、乾燥を嫌うとされています。
肺の働きを守るためには、こまめな水分補給と、体の内側から潤す食材を摂ることが大切です。
たとえば:
- 白きくらげ、れんこん、はちみつなどの潤い食材を取り入れる
- はちみつ湯や白湯で喉を保湿
- 部屋の加湿(洗濯物の室内星も効果的)
- 目の乾燥予防に、スマホやPCは長時間連続使用しない
潤いは肺を守り、乾燥から体を守る‟天然のバリア”になります。
空気が乾きやすいこの季節こそ、意識して潤すことが、秋の養生につながります。
③ゆったりと秋を感じて、心をほぐす時間
秋の空気には、どこか静けさと寂しさが漂います。
寒露の頃は、心も少し感傷的になりやすい季節です。
でも、こうした気持ちは自然の流れの一部。
無理に元気になろうとせず、今感じていることをやさしく受け止めてみましょう。
心の養生のコツ
- 自然の香り、ゆったりと流れる音楽、やわらかな温もりで、心に静かな癒しを届ける
- スマホを手放し、手帳にその日の気持ちを書いてみる
- 美しい秋の風景を楽しむ(紅葉、秋の空、金木犀の香りなど)
秋は、自然が色を落とし、静けさを取り戻してくように、私たちの心や暮らしも整えたり、不要なものを手放したりしやすくなる季節です。
心をゆるめ、次の季節に向けた土台をゆっくり整えていきましょう。

4.寒露におすすめの食材&生活習慣
①おすすめ食材
- さつまいも:やさしい甘みとホクホクとした食感が魅力の秋の味覚。
脾(=消化器系)を補い、腸を潤す食材とされ、胃腸の働きを助けながら便通を整える作用があります。
秋は乾燥とともに冷えも感じやすく、腸の働きが鈍くなり便秘がちになる人もいます。
そんなとき、温かい焼き芋や煮物、さつまいも入り味噌汁などで、内側からじんわり体を温めてみてください。
皮ごと食べることで、食物繊維やポリフェノールも摂ることができます。 - 栗:腎を補い、下半身の冷えやだるさ、足腰の弱りに働きかけるとされる食材です。
腎は生命エネルギーの源とされ、冷えや疲れが出やすい秋は、特に意識して整えたい働きのひとつです。
栗ご飯や煮物にして取り入れると、滋養をつけて、疲れや冷えから体を守ってくれます。
まろやかな自然な甘みで、秋のおやつにもぴったりです。 - 秋刀魚:秋に旬を迎える秋刀魚は、東洋医学では「血を補う魚」とされ、肌や粘膜の乾燥、目の疲れ、喉の不快感など、秋に起こりやすい不調の改善に役立つといわれています。
脂質も豊富で、エネルギー補給や疲労回復にも効果的です。
塩焼きに大根おろしを添えると、消化の助けにもなり、バランスの取れた一皿になります。
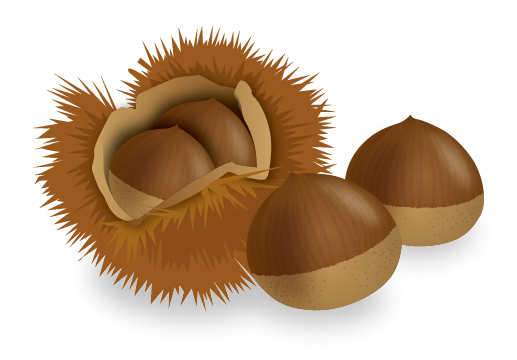
②おすすめの生活習慣
- 朝の光を浴びて体内時計を整える
日が短くなる季節こそ、朝の時間を意識して過ごしましょう。
カーテンを開けて朝日を浴びたり、軽く散歩したりするだけでも、体内のリズムが整い、気分もすっきりします。 - お風呂で心と体を温め、リラックス
ぬるめのお湯にゆったり浸かることで血流が良くなり、リラックス効果も得られます。
アロマや入浴剤のやさしい香りを取り入れて、心身を静かに整える - 軽めの運動で巡りを良くする習慣を
ウォーキングやラジオ体操、寝る前のストレッチなど、無理のない運動を習慣にしましょう。
寒さが本格化する前に体力を整えておくことで、冬を元気に迎える準備ができます。 - 自然の変化を五感で味わう時間をもつ
金木犀の香り、落ち葉の音、秋空の美しさ…。
自然の移ろいを感じる時間は、心にゆとりを与え、気持ちを穏やかにしてくれます。
日々の中に、小さな季節の喜びを見つけてみましょう。
5.おわりに
寒露は、心も体も少しずつ「内へ向かうモード」に切り替わっていく季節です。
ペースを少しゆるめて、自分の調子に目を向けてみましょう。
首元を温める、温かい食べ物をゆっくり楽しいむ、秋の風を感じながら深く息をする。
そんな一つひとつが、冬を迎えるための自然な準備となります。
忙しさの中でも自分を急がせず、秋の静けさを味方にしながら、自分にとっての心地よさをみつけてみてください。
ご予約について
完全予約制となっております。
ご予約は店舗へのお電話、またはご予約受付にて承っております。
お問い合わせメールの場合、返信にお時間をいただく場合がございます。
お急ぎの場合はお電話がおすすめです。
ご予約受付
ご相談について
漢方相談では、今のお体の状態や気になる症状について、丁寧にお話をお伺いします。
落ち着いた相談スペースで、リラックスしてご相談いただけますので、初めての方もご安心ください。
体質やお悩みに合わせて、ぴったりの漢方薬をご提案いたします。
ご相談時間はお一人30分くらいです。
松山漢方相談薬局HP
店舗情報
松山漢方相談薬局 横浜桜木町店
- 営業時間:10:00~20:00
- 定休日:第2木曜日
- TEL:045-341-4823
- 〒231-0063
神奈川県横浜市中区花咲町1丁目19-3
セルアージュ横濱桜木町ヴァルール101号室
松山漢方相談薬局 鶴見店
- 営業時間:10:00〜20:00
- 定休日:第2木曜日
- TEL:045-718-6801
- 住所:〒230-0062
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2-2
鶴見フーガII 3階

















