芒種(ぼうしゅ)とは?(2025年6月5日~6月20日)
芒種(ぼうしゅ)は、二十四節気の9番目にあたり、毎年6月5日頃にあたります。
「芒(のぎ)」とは、稲や麦の穂先にある細かい毛のことで、その種をまく目安となることからこの名が付きました。
芒種は「麦の穂が出る頃」とも言われ、田植えや麦の収穫など夏の農作業が本格的に始まる時期として、農家にとって一年で最も忙しい季節の一つとされてきました。
この時期は、初夏の気配が強まり、日差しが徐々に強くなってきますが、日本の多くの地域では湿気の多い梅雨の季節と重なるため、天候がぐずつきがちです。この湿気が私たちの体に大きな影響を及ぼすため、芒種の時期の養生は、「湿邪(しつじゃ)」を取り除き、体調を整えることが大切となります。
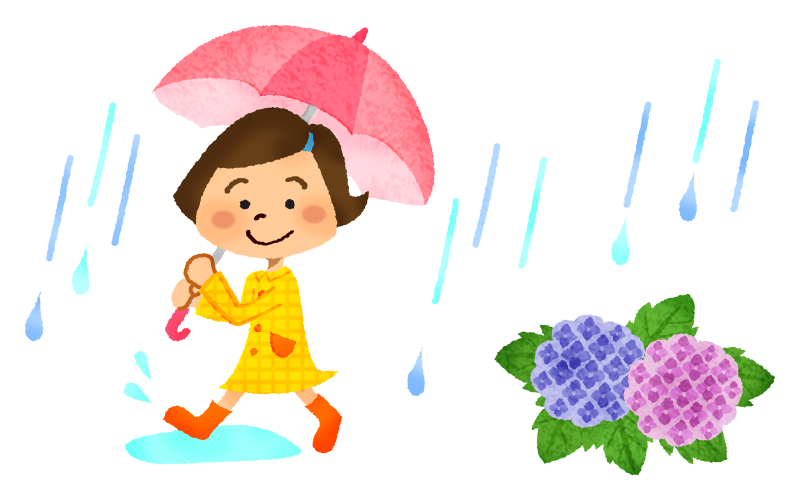
梅雨の湿気が体に与える影響とは?
梅雨の季節は、空気中の湿度が高く、ジメジメとした環境が続きます。この湿気が体内に入り込み「湿邪」となって停滞すると、さまざまな体の不調が現れます。
東洋医学では、湿邪は「重くて粘り強い」とされ、体を重くだるく感じさせたり、関節や筋肉の痛みを増幅させたりします。
主な症状として、
- 全身のだるさや疲労感
- むくみやすくなる
- 関節の痛みやこわばり
- 食欲不振、胃腸の不調
- 頭がぼんやりしやすい
- 精神的な憂うつ
などが挙げられます。湿邪は水分代謝を乱すため、体内に余分な水分が溜まりやすく、体重増加や肌のべたつきやかゆみなども感じることがあります。
芒種の養生法:湿気に負けない生活習慣
1.住環境の整備:湿気対策を徹底する
まずは、住まいの環境から見直しましょう。梅雨時期の湿度は、室内のカビやダニの発生も促すため、健康への悪影響も大きいです。
湿気を溜め込まないポイント!
- こまめな換気:雨が降っていない時間帯を見計らって、窓を開けて空気を入れ替える。
- 除湿器の活用:湿度が70%以上になると不快感が増すため、除湿器やエアコンの除湿機能を使って、湿度を50~60%にコントロールする。
- 布団や衣類の湿気対策:寝具は天気の良い日に天日干しし、衣類は乾燥機や除湿剤を使う。
- こまめな掃除:カビの発生源となるホコリを掃除機や拭き掃除で減らす。
これらの環境管理が、まず土台となります。
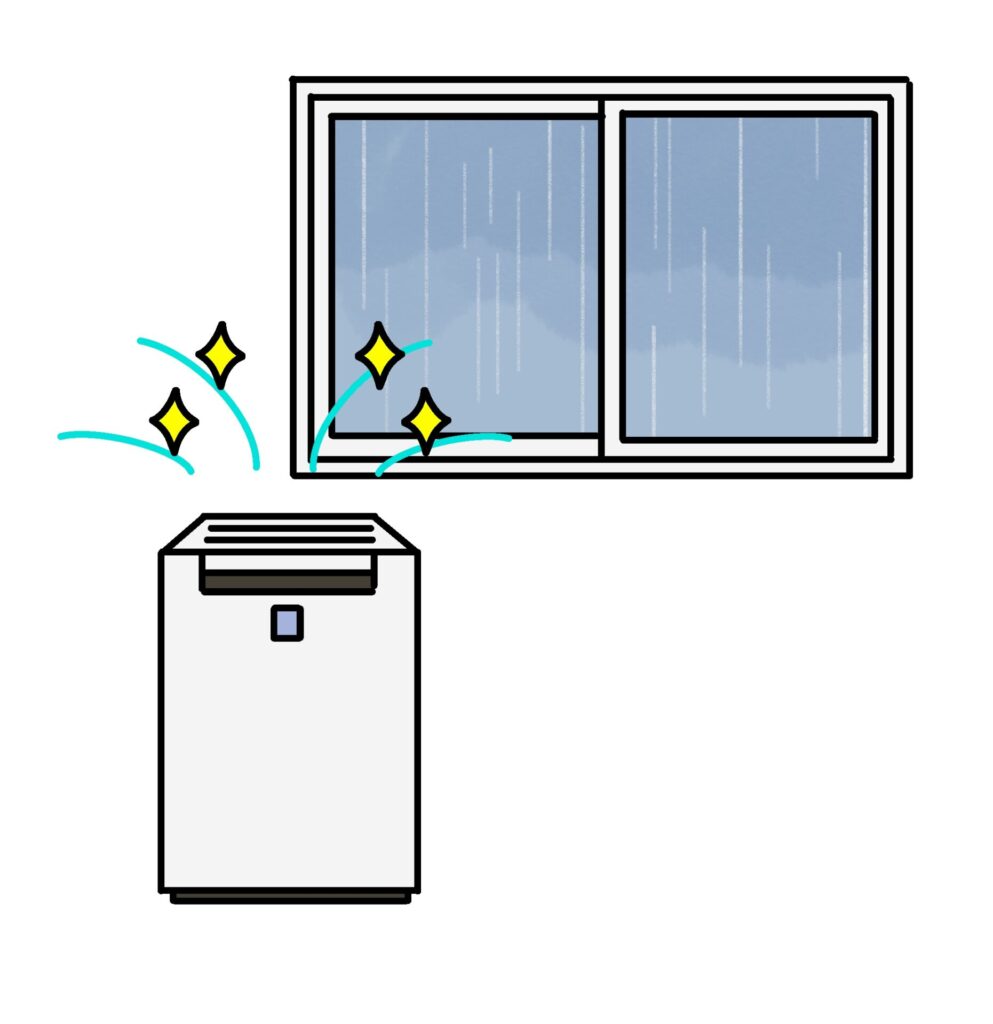
2.食事で養生:湿気を除き、胃腸を助ける
湿気で最も影響を受けやすいのは、消化器官です。胃腸の働きが鈍ると食欲不振や体調不良を招きます。梅雨時期は、以下の点に気を付けると良いでしょう。
- 温かく消化に良い食事を心掛ける
冷たい飲食物や脂っこいものは、胃腸に負担がかかりやすいため控えましょう。
温かいスープやおかゆ、煮物などが適しています。 - 発汗を促し、体の湿気を出す食材
生姜、山椒、シナモン、紫蘇、陳皮(みかんの皮を乾燥させたもの)など
体を温め、湿気を取り除く効果があるとされています。特に生姜は、日常の料理に加えやすいのでおすすめです。 - 利湿作用のある食材を取り入れる
きゅうり、ズッキーニ、とうもろこし、はと麦、緑豆、みょうが など
余分な水分を排出し、むくみを軽減します。 - 消化促進のために少量多回食を意識する
一度に大量に食べると胃腸に負担がかかるため、少量を複数回に分けて摂るのが理想的です。
3.適度な運動と入浴:体の気血を巡らせる
湿度によって体が重く感じると動くことが億劫に感じますが、適度な運動はとても重要です。
- 軽いストレッチやウォーキング
血液やリンパの流れを促し、体内の余分な水分や老廃物の排出を助けます。 - ぬるめのお湯で入浴(38℃~40℃程度)
熱い湯に長時間浸かるのは、逆に体を疲れさせるので避けましょう。
この時期は、体表の汗だけでなく、体の奥から汗をかくことが大切です。肩まで浸かり、リラックスしながら血行を良くしましょう。入浴後は、体をしっかりと拭き、湿気で冷えないよう注意が必要です。

4.休息と睡眠:自然のリズムに合わせる
湿気や気温の変化が自律神経に影響を与えやすいため、ストレスを溜めないことが重要です。
規則正しい生活を送り、十分な睡眠を確保することで、身体の回復力が高まります。
梅雨の長雨は、気分も沈みやすいので、こまめに気分転換をしながら心身のバランスを整えましょう。
心の養生:梅雨の気分の乗り切り方
梅雨の季節は、日照時間が減り、気分が落ち込みやすくなります。心と体は密接に関わっているため、心のケアも重要です。
- 自然光をできるだけ浴びる
雨の日でも窓際で過ごす、散歩に出るなどしてセロトニンの分泌を促しましょう。 - 趣味やリラックス法を持つ
読書、音楽、アロマテラピーなど、自分が落ち着ける時間を持つことが大切です。 - 適度に体を動かす
運動は、エンドルフィンの分泌を促し、ストレス解消に効果的です。

さいごに
芒種の時期は、農作業が本格化し自然が最も活発に動き出す季節です。しかし日本の多くの地域では、湿度の高い梅雨と重なるため、私たちの体も心も湿気に負けやすくなります。この時期の養生は「湿邪」を取り除き、胃腸を整え、体内の水分代謝を正常に保つことがポイントです。
夏を元気に迎えるために、住環境の工夫、湿気を除き胃腸を助ける食事、適度な運動と休息を心がけることで、梅雨の不調を防ぐことが大切です。
芒種は、自然のリズムに合わせて、身体も心もゆったりと養う時期。湿気と上手に付き合い、健やかな毎日を過ごしましょう。
芒種の時期にぴったり!「梅しごと」
この時期になると青梅が店頭に並び始め、昔から伝わる「梅しごと」のシーズンがやってきました。
梅しごとの一つである梅シロップ作り。梅シロップは、下ごしらえした梅を砂糖や氷砂糖と一緒に付け込んで作る甘酸っぱいシロップです。
最大の特徴は、梅に豊富に含まれる「クエン酸」です。クエン酸は、体内のエネルギー代謝を促進し、疲労の原因となる乳酸を分解して疲れを軽減する働きがあります。そのため、特に夏の暑さや運動後の疲労回復に効果的です。
また、梅には有機酸やポリフェノールも含まれ、これらには抗菌・抗酸化作用があります。
抗菌作用により食中毒予防や免疫力の向上を助け、抗酸化作用は体の老化を防ぐサポートをします。
さらには、梅の酸味は唾液の分泌を促し、消化を助けることで胃腸の調子を整える効果も期待されます。
水や炭酸水で割って飲むことで、手軽に水分とミネラルを補給できるため、熱中症予防にも役立ちます。甘酸っぱい味わいは子ともから大人まで好まれ、夏の暑さで食欲が落ちた時の栄養補給にも適しています。
このように、梅シロップは疲労回復や消化促進、免疫力強化など多くの健康効果が期待できる自然の恵みです。ぜひ、この季節ならではの味わいを楽しみながら、梅シロップづくりに挑戦してみてください。

ご予約について
完全予約制となっております。
ご予約は店舗へのお電話、またはご予約受付にて承っております。
お問い合わせメールの場合、返信にお時間をいただく場合がございます。
お急ぎの場合はお電話がおすすめです。
ご予約受付
ご相談について
漢方相談では、今のお体の状態や気になる症状について、丁寧にお話をお伺いします。
落ち着いた相談スペースで、リラックスしてご相談いただけますので、初めての方もご安心ください。
体質やお悩みに合わせて、ぴったりの漢方薬をご提案いたします。
ご相談時間はお一人30分くらいです。
松山漢方相談薬局HP
店舗情報
松山漢方相談薬局 横浜桜木町店
- 営業時間:10:00~20:00
- 定休日:第2木曜日
- TEL:045-341-4823
- 〒231-0063
神奈川県横浜市中区花咲町1丁目19-3
セルアージュ横濱桜木町ヴァルール101号室
松山漢方相談薬局 鶴見店
- 営業時間:10:00〜20:00
- 定休日:第2木曜日
- TEL:045-718-6801
- 住所:〒230-0062
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2-2
鶴見フーガII 3階

















