1.小暑とは?(2025年7月7日~7月21日)
二十四節気の一つ「小暑(しょうしょ)」は、毎年7月7日ごろに訪れます。梅雨が明けると、日差しは一気に強まり、空も空気も夏らしく変わっていきます。今年は梅雨明けが例年よりも早く、すでに夏の気配が色濃く感じられる地域も多いのではないでしょうか。
自然が勢いを増す一方で、私たちの体と心には、目には見えない負担がかかり始める季節でもあります。
「なんとなく調子が悪い」「朝から疲れている」「夜、ぐっすり眠れない」といった不調を訴える人が増えてくるのも、この時期の特徴です。
本格的な夏の入り口である「小暑」は、体と心の‟夏支度”を始めるための大切なタイミング。
今回は、この時期を元気に過ごすためのケアのヒントをご紹介します。

2.梅雨明け後の気候がもたらす、体と心への負担
①熱中症・脱水症のリスクに注意!高温多湿が引き起こす危険
梅雨が明けると、空は一気に夏模様。けれど、空気がカラッとするどころか、近年では高温多湿の不快な日々が続きます。汗をかいても蒸発しにくく、体に熱がこもりやすくなることで、熱中症や脱水症のリスクが高まります。
熱中症の初期症状
- めまい、頭痛
- 倦怠感
- 吐き気
- 手足のしびれや筋肉のこむら返り など
重症化すると、意識障害や痙攣を引き起こすこともあるため、早めの対策が重要です。

脱水症状
- 口の渇き
- 尿量減少、濃い尿
- 疲労感
- 頭痛
- 集中力低下 など
水分とともに塩分・ミネラルをバランス良く補い、冷たい飲み物に偏りすぎず、こまめな水分補給を心がけましょう。
外出や運動は、無理をせず涼しい時間帯に!
②自律神経のバランスを崩す『温度差ストレス』
冷房の効いた室内と、外の猛暑との温度差は、自律神経に大きなストレスを与えます。
体温を調節する自律神経は、気温差に絶えず対応しようとすることで疲弊し、心身のバランスを崩す原因になります。
よくある不調のサイン
- 倦怠感、疲れやすさ
- 食欲の低下、胃の不快感
- 頭がぼーっとする、めまい
- 気分の落ち込み、イライラ
- 睡眠の質の低下(寝つきが悪い、途中で目が覚める)など
この時期の「なんとなく不調」は、自律神経の乱れが関係していることが多くあります。
対策のコツ
- 冷房の設定温度は26~28℃、湿度は50~60%が理想
- 冷風が直接体に当たらない工夫
- 羽織やストールなどで体温調節をする
- 汗をかいたらしっかり拭き、体を冷やし過ぎない
③寝苦しい夜が続くと、心まで疲れてしまう
熱帯夜が続くと眠りが浅くなり、翌日のパフォーマンスや心の安定にも影響を与えます。
「いつもよりイライラしやすい」「ぼんやりして集中できない」——こうした不調の原因には、睡眠の質の低下が関係しているのかもしれません。

快眠のヒント
- 理想の寝室環境(室温26~28℃、湿度50~60%)
- 就寝1~2時間前にぬるめ(38~40℃)の湯船に浸かることで、副交感神経が優位になり眠りやすくなる
- 寝具は通気性のよい素材を選ぶ(麻やガーゼなど)
- エアコンは「除湿」モードやタイマー機能などを活用
- 寝る1時間前はスマホやPCを避け、脳をクールダウン
④夏バテの入り口
夏バテというと真夏に起こるものと思われがちですが、実は小暑の頃からすでに兆しが現れ始めます。
夏バテの前兆
- 食欲不振
- 倦怠感、疲れが取れない
- 頭痛、めまい、ふらつき
- 睡眠の質の低下
- イライラ、集中力の低下
- 胃腸のトラブル(便秘、下痢、胃もたれ、吐き気 など)
- 体がむくみやすくなる
- 微熱、体温調節の異常 など
冷たい飲み物や食事ばかりでは、体を冷やし過ぎてしまいます。
温かい味噌汁やお粥などで内臓をいたわりながら、少しずつ栄養を補っていくことが大切です。
3.『水・食・動・休』を整える(体を整えるケア)
体調を崩しやすい時期だからこそ、日々の暮らしの中で‟小さな養生”を心がけましょう。
①水(水分補給):常温で塩分とミネラルも意識
暑いからといって、冷たい飲み物ばかり飲んでいませんか?
冷たい飲み物ばかり摂取していると内臓が冷え、代謝が落ちる原因にもなります。
おすすめの飲み方
- 常温の水や麦茶を少しずつこまめに飲む
- レモン水や梅干し入り水でミネラル補給
- スポーツドリンクより、自然に近い形で補給できる飲み物が体に優しい

②食(食事)の見直し:苦みと酸味でバランスをとる
東洋医学では、季節ごとに体の調子を整えるのに適した「味」があるとされています。夏は「苦味」と「酸味」が体に良いと考えられています。
- 苦み:ゴーヤ、ピーマン、青じそ など
→体の熱を冷まし、胃腸の働きを整える - 酸味:梅干し、酢の物、柑橘類 など
→汗で失われがちな気(エネルギー)を守り、体の内側から整える

これからどんどん暑くなりますが、冷たいものの摂り過ぎには気を付け、温かい食事でのエネルギー補給を心がけましょう。
食欲がない時こそ、温かいスープやお粥など、消化に優しく栄養があるものを摂ると良いです。
③動と休(生活習慣):汗をかいて、休んで、整える
冷房の効いた室内にいると、汗をかく機会が減り、代謝が落ちてしまいます。
「意識的に汗をかく」ことが、夏の体調管理ではとても大切です。
- 早寝早起きを意識して体内時計をリセット
- 夜はシャワーで済ませず、湯船に浸かって汗をかく
(汗をかいて、体内にたまりやすい余分な水分(湿気)を排出) - 朝夕の涼しい時間帯に軽く体を動かす
(散歩やストレッチなど)
4.夏のストレスとうまく付き合う(心のケア)
夏は体だけでなく、心もストレスを感じやすい季節です。
自分でも気づかないうちに、心が疲れていることがあります。
「イライラする」「集中できない」「なんだか気分が沈む」——それも夏の始まりに多い心の症状です。
①自然に触れて、心のスイッチを切り替える
朝の光を浴びながらの散歩。木陰で一息。
それだけでも自律神経は整い、心が落ち着きます。
「自然のリズム」に触れることが、手軽で効果的なセルフケアです。
②呼吸と香りの力を活かす
深呼吸で心身の緊張をほぐし、香りで癒し効果をプラス。

おすすめの呼吸法
仕事中や外出先で瞬時にリフレッシュしたいときには【4-2-6呼吸法】
リラックスしたいときや寝る前には【4-7-8呼吸法】
1.姿勢を整える(背筋を伸ばし、リラックス)
2.鼻から息を吸う(4秒かけてお腹を膨らます)
3.息を止める(2秒または7秒)
4.口から息を吐く(6秒または8秒かけてお腹を凹ませる)
5.繰り返す(3~10回程度)
おすすめのアロマ
- ラベンダー(安眠、リラックス)
- ペパーミント(清涼感、集中力アップ)
- 柑橘系(気分転換、明るい気持ちに)
心が落ち着く香りを、寝る前や気分が落ち着かない時に取り入れてみてください。
③『頑張らない』ことを選ぶ勇気も
夏はイベントや予定が増え、ついスケジュールを詰め込みがちです。けれど、少し余白を残すことが、疲れずに過ごすための大切なコツでもあります。「やらない」と決めることも、立派なセルフケア。無理に詰め込まない選択が、心と体を守ってくれるのです。
5.おわりに
小暑は夏の入り口。暑さが本格化し始め、知らず知らずのうちに体と心に疲れが溜まりやすくなる時期です。だからこそ、この時期は少し立ち止まって、自分の内側と向き合う良いチャンスです。
「なんとなく疲れている」「なんとなく体調が悪い」「いつのよりイライラしやすい」——それは、季節の変わり目に体が発しているサインかもしれません。
冷たいものを摂り過ぎない。眠る前のスマホを手放す。朝の光を浴びて深く呼吸をする。
こうした小さな積み重ねが、夏を元気に乗り切る力になります。
無理をせず、自分のペースで。健やかで穏やかな夏を迎えられますように。
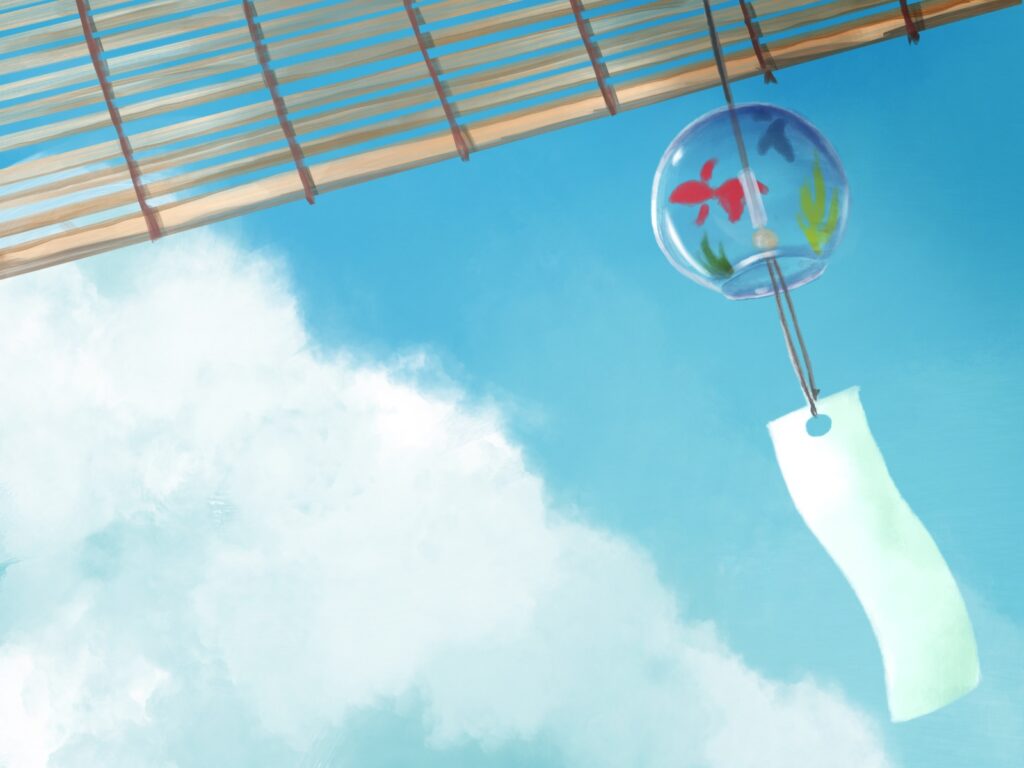
ご予約について
完全予約制となっております。
ご予約は店舗へのお電話、またはご予約受付にて承っております。
お問い合わせメールの場合、返信にお時間をいただく場合がございます。
お急ぎの場合はお電話がおすすめです。
ご予約受付
ご相談について
漢方相談では、今のお体の状態や気になる症状について、丁寧にお話をお伺いします。
落ち着いた相談スペースで、リラックスしてご相談いただけますので、初めての方もご安心ください。
体質やお悩みに合わせて、ぴったりの漢方薬をご提案いたします。
ご相談時間はお一人30分くらいです。
松山漢方相談薬局HP
店舗情報
松山漢方相談薬局 横浜桜木町店
- 営業時間:10:00~20:00
- 定休日:第2木曜日
- TEL:045-341-4823
- 〒231-0063
神奈川県横浜市中区花咲町1丁目19-3
セルアージュ横濱桜木町ヴァルール101号室
松山漢方相談薬局 鶴見店
- 営業時間:10:00〜20:00
- 定休日:第2木曜日
- TEL:045-718-6801
- 住所:〒230-0062
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2-2
鶴見フーガII 3階

















