医学の父ヒポクラテスは「すべての病気は腸からはじまる」と言いました。
発生学では、お母さんのお腹の中で脳や心臓よりも先に、腸ができるといわれています。
そんな重要な臓器を育む『腸活』という言葉が近年話題になっています。
ここでは腸活を始めたいあなたに知っておいて欲しい、腸活の考え方・目的について東洋医学の視点も踏まえて全2回にわたってお話していきます。
腸活は何のために必要?
腸にはどんな働きがあるか、知っていますか?
食べたものの消化・吸収・排泄に関わるのはもちろん、からだを守る免疫の大部分を担う場所でもあります。
お通じが悪いと「腸が悪いのかな~。」
風邪を引きかけると「免疫力弱っているなー。」
などと思う人も少なくないでしょう。
腸の状態が影響するのはそれらだけではなく、肥満や高血圧、糖尿病、がんなどの生活習慣病、うつ病、認知症などの発症にも関わっていることがわかっています。
最近では『腸疲労』という言葉もあり、腸にトラブルを抱える人が増えています。
全身の臓器に影響を及ぼしかねない腸内環境の重要性、もうお分かりでしょうか・・・
腸内環境・腸内細菌のはなし
腸内環境の「腸」ってどこ?
「腸」といっても腸がつく部分はたくさんあります。
よく耳にする「腸内環境」「腸内細菌」などの腸は、一般的に大腸のことをいいます。(小腸にも細菌はいますが、大腸に比べて少ないです。)
また、腸の中の状態を顕微鏡で見ると花畑のように見えることから『腸内フローラ』と呼ばれたりもします。
この腸には、100種類・100兆個以上の細菌がいるといわれています。

腸内細菌はどこからくるの?
お母さんのお腹の中にいる段階ではわたしたちの腸は無菌状態です。
お母さんのお腹から出てくるとき、産道を通るとお母さんの腸内細菌を獲得することができます。
そのため、お母さんの腸内環境がその後の赤ちゃんの腸内環境に大きな影響を与えることがわかりますね。
一生を通して腸内細菌の種類はほぼ変わらない?!
わたしたちの腸は、まずお母さん由来の腸内細菌が選択的に定着します。
その後の生活環境や食事などによって自然に細菌を取り込んだり排除したりすることで成長とともに変化し、3歳頃に成人並の腸内フローラが完成することがわかっています。
その約3年間で定着した腸内細菌の種類は一生を通してほぼ変わらないといわれています。
食事や生活習慣、抗生物質の使用などにより善玉菌や悪玉菌のバランスが変化することはありますが、種類が増えたり減ったりしないということです。
つまり、外から新たな菌を入れ定着させるのは困難なことだと考えられます。
それなら今いる菌を増やそうと思いますよね。
しかしわたしたちの腸内フローラはみんな違いますし、それぞれどんな菌から構成されているかなんてわかりません。
ひとくちに「乳酸菌」といっても、乳酸を生み出す菌をまとめて呼んでいるのであって、実際は数百種類もの乳酸菌が存在するといわれています。
例えば話題のヨーグルトで、その乳酸菌のうちのたった数種類を摂取しても確率から考えて腸への有用性はかなり低いと思います。それを何百回と試して効果を比較するのは現実的ではありません。
皆さんが一度は耳にしたことがありそうな、「生きて腸まで届く」は乳酸菌入りヨーグルトのキャッチコピーですね。
実際に100%が腸まで届くことはなく、ほとんどが胃酸により死滅してしまいます。
しかし、菌の死骸が善玉菌のエサになることで無意味であるとは言い切れません。
『自分の腸内フローラを大切にはぐくむこと』が腸活!
外から入れた細菌は定着しづらいことから、元々持っている腸内細菌を活かすことを考えましょう。
腸内環境を整えることで、腸内細菌のバランスを良い状態に保つことができます。
善玉菌・悪玉菌と“グレー”な菌
腸に存在する細菌すべてが善か悪か、白黒はっきりするわけではありません。
実は、グレーな細菌も存在します。
それは『日和見(ひよりみ)菌』と呼ばれています。
善玉菌:悪玉菌:日和見菌の理想的なバランスは、
2 : 1 : 7 だといわれています。
このグレーな細菌は、善玉菌・悪玉菌のバランスによって善にも悪にもなり得ます。
善玉菌が多ければ善玉菌に加勢しますが、逆も然りです。
何事もバランスが重要なのです。
ここで、善玉菌・悪玉菌の例をあげましょう。
善玉菌・・・乳酸菌、ビフィズス菌
悪玉菌・・・ウェルシュ菌、ブドウ球菌、ピロリ菌、大腸菌(菌種によっては日和見菌)
そもそも何を根拠に善か悪かを決めているのか、気になりませんか?
善玉菌は腸での消化や吸収を助けたり便通を改善したりする菌のことをいい、
悪玉菌は腸でタンパク質を腐敗させ有害物質を発生させる菌のことをいいます。
本来であれば悪玉菌が健康に害を及ぼすことはありませんが、善玉菌よりも悪玉菌が増えていくとさまざまな病気のリスクになります。
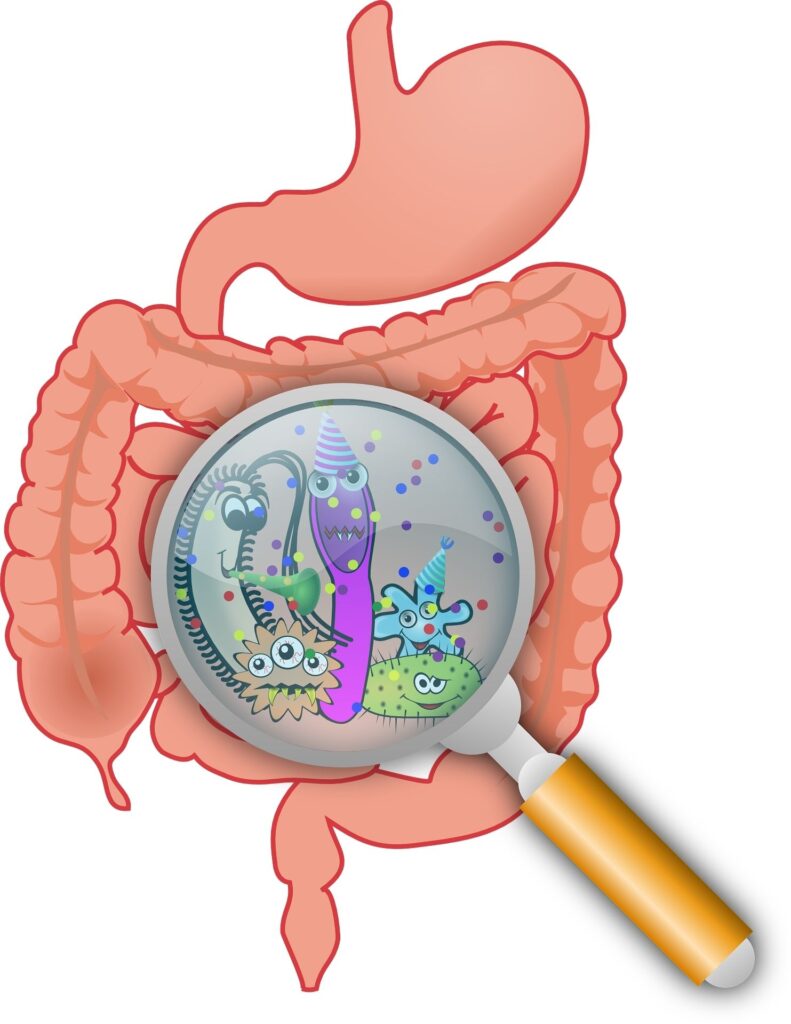
悪玉菌が病気のリスクになるワケ
悪玉菌が直接的にすべての病気の原因となっているわけではありません。
まず、悪玉菌が増殖することで便秘になると、悪玉菌が生成した有毒物質が排出されにくくなります。
その有害物質が腸から血液に溶け込むことで全身を巡り、様々な悪影響を引き起こします。
中には菌そのものが病気の原因になっている場合もありますが、それはほんのわずかです。
最近では大腸がんや結腸がんの原因となる有害性の高い悪玉菌も見つかっています。
脳腸相関
『脳腸相関』という言葉を聞いたことがありますか?
脳と腸は直接管などでつながっているわけではありませんが、自律神経やホルモンを介して、双方向(脳⇔腸)のネットワークがあるといわれており、互いに良い影響も悪い影響も与えてしまいます。
「ストレスを感じるとお腹が痛くなる」
「便秘が続くと気分が落ち込んでしまう」
こんな経験をしたことがある人も多いのではないでしょうか。
近年の研究によると、腸の不調とうつ病、自閉症、認知症との関連が示唆されており、腸内環境のコントロールが認知機能や精神神経症状にも影響するという考え方が進んでいます。
つまり、腸活は脳に関連した疾患の予防や治療に役立てる手段のひとつになり得るかもしれません。
腸肝循環の障害
また、『腸肝循環』という食べたものや薬物などの物質が腸→肝臓に戻るシステムが存在します。
ここで腸内細菌が物質の形を変える手伝いをしますが、腸内環境の悪化によりそれが不十分になってしまうと腸肝循環が乱れ、肝臓に負担がかかって肝障害を引き起こすこともあるといわれています。

どうして悪玉菌は増えるのか
悪玉菌が増える要因として、3つ考えられます。
・加齢によるもの
生活習慣の積み重ねが腸内環境をつくっていくと考えられます。その習慣が長くなればなるほど、良い影響も悪い影響も大きく出てきます。
・タンパク質の過剰摂取
そもそも悪玉菌が悪者扱いされている原因は、タンパク質を腐敗させ有害物質を発生させるからです。
このタンパク質が過剰になると悪玉菌の働きも活発になり、発生する有害物質も多くなるのは自然なことでしょう。
・腸内のアルカリ化
わたしたちのからだは、部位ごとに酸性~アルカリ性のちょうどいい状態でいるのが理想的です。
例えば、ボディソープのCMでは『弱酸性の~』なんて言葉が使われていたりするように、肌は外部からの刺激から守るために弱酸性が良い状態です。
また、胃では胃酸が分泌されるためその名の通り酸性となります。
胃から下の腸では、消化液の影響により弱アルカリ性となりますが、腸内細菌の影響を受けるため変化します。
善玉菌は酸性の物質を作り出すため酸性に傾けます。
そのため、善玉菌の多い(=腸内環境が良好な)場合は弱酸性になります。
反対に悪玉菌はアルカリ性に傾ける性質があります。
さらにアルカリ性の状態が続くと悪玉菌が増殖しやすくなり腸内環境の悪化につながります。
つまり、腸を弱酸性にすることが悪玉菌を抑え、善玉菌の力を発揮するのにも良い環境といえますね。

腸内細菌が漢方薬の効き目を左右する?!
漢方薬は、複数の生薬(植物や鉱物、動物の薬効のある部位)が組み合わさってできています。
生薬の中には『配糖体』と呼ばれる成分がありますが、そのままでは体に吸収されにくい特徴を持ちます。
薬の効果を発揮するためには、わたしたちのからだの中でそれを吸収しやすい形に変換する必要があります。
「糖とそれ以外」に分解する必要があり、この作業を行うのが腸内細菌です。
配糖体の種類によっては特定の菌にしか変換できないこともあり、腸内細菌の存在の有無によって漢方薬の効き目に影響を及ぼすといえます。
微生物に着目した『腸活』
一般的な腸活の方法として、『○○バイオティクス』という言葉があります。
バイオティクス(biotics)とは、“健康に役立つ生きた微生物”という意味があります。
微生物の働きによって3種類に分けられていますので、それぞれみていきましょう。
プロバイオティクス(いい菌を摂る)
外から新たな菌を入れて定着させるのは難しい・・・
しかし、菌を入れることが無意味だとは思いません。
発酵食品などから有用な菌をとることをプロバイオティクスといいます。
納豆菌やビフィズス菌、乳酸菌などがこれにあたります。
納豆やキムチ、味噌、醤油も発酵食品ですね。

プレバイオティクス(菌のエサを摂る)
善玉菌が好むものを食べることにより、それが善玉菌のエサになると考えられます。
エサが不足すると腸の表面を覆う粘液を食べる菌が存在し、それにより粘液が減り、腸の異物に対するブロック機能が落ちることがわかっています。そのためにもエサを与えることは非常に重要です。
特に食物繊維やオリゴ糖などがエサにあたります。
オリゴ糖の中でも「消化性」と「難消化性」のうち、難消化性のものは大腸まで消化されずに届きます。
難消化性のオリゴ糖はバナナやごぼう、たまねぎなどに含まれます。

ポストバイオティクス(菌が生む成分を助けるものを摂る)
これは新たな腸活の考え方であり、腸内細菌が生み出す有用な物質にフォーカスした方法です。
その有用な物質とは、『短鎖脂肪酸』です。
短鎖脂肪酸とは総称で、酢酸や酪酸、プロピオン酸などを指します。
この短鎖脂肪酸は腸の中で有用な菌の生育に良い環境を作ってくれます。
また、できた短鎖脂肪酸を別の菌が材料にしてまた新たな短鎖脂肪酸を作っていくこともわかっています。
ビタミンB群、オメガ3(n-3系)脂肪酸などの摂取がポストバイオティクスにあたります。
ビタミンBはエネルギー代謝に関わります。
特にビタミンB1(チアミン)は短鎖脂肪酸の生成に不可欠です。
豚肉や大豆、玄米、ナッツ類に豊富に含まれています。
またオメガ3(n-3系)脂肪酸は、腸内細菌で代謝されると抗炎症作用のある物質が生まれるといわれており、従来知られている効果だけでない有用性がわかってきています。
魚だけでなく亜麻仁油、えごま油などにも含まれていますので、選ぶ油の種類にも気を配ってみるといいかもしれませんね。

バカにしないでほしいウンチの存在
腸活をするきっかけは人によってさまざまだと思います。
しかし腸活がうまくいっているかどうかは、体感だけでは判断しにくいところもあるでしょう。
ひとつ、共通して目に見える指標として「便」があります。
当たり前のように流してしまっているのはもったいないので、まずは便を知ることから始めましょう!
うんちを作るのは食べカスだけじゃない
食べたものがうんちになる、それは間違いありません。
しかし、うんちの全てが食べカスというわけではないのです。
実は、理想のうんちでも
約80%・・・水分(下痢だと90%、コロコロでも70%)
残り20%のうち、
5%・・・食べかす
15%・・・腸内細菌や剥がれ落ちた腸の粘膜であるといわれています。
からだの細胞は日々生まれ変わっており、腸もそのひとつです。
生まれ変わる周期は部位ごとに異なり、小腸は約3日、大腸は約10日、皮膚は約1ヶ月、筋肉は約2ヶ月、血液は約4ヶ月、骨は約5ヶ月といわれています。
小腸や大腸は他の部位に比べて特に周期が短く、生まれ変わりが激しいと分かります。
つまり、水分量はもちろんですが腸内細菌の豊富さ・腸の粘膜の生まれ変わり(新陳代謝)がうんちの状態を左右するということです。
うんちはからだからの“お便り”
うんちは体調のバロメーターともいわれています。
色や形、やわらかさ、におい、量など、うんちから分かる情報はたくさんあります。
それらの変化から病気の早期発見につながることもあるといわれています。
近年は用を足すと自動で水が流れるトイレが増えており、うんちを見る間もない人もいるかもしれません。
自身の体調とうんちの状態を意識してみるといいかもしれませんね。
ちなみに、食べたものが便になって出るまで約24~48時間かかるといわれていますので、ぜひ目安にしてみてください。
次回に続きます🌞
ご予約について
完全予約制となっております。
ご予約は店舗へのお電話、またはご予約受付にて承っております。
お問い合わせメールの場合、返信にお時間をいただく場合がございます。
お急ぎの場合はお電話がおすすめです。
ご予約受付
ご相談について
漢方相談では、今のお体の状態や気になる症状について、丁寧にお話をお伺いします。
落ち着いた相談スペースで、リラックスしてご相談いただけますので、初めての方もご安心ください。
体質やお悩みに合わせて、ぴったりの漢方薬をご提案いたします。
ご相談時間はお一人30分くらいです。
松山漢方相談薬局HP
店舗情報
松山漢方相談薬局 横浜桜木町店
- 営業時間:10:00~20:00
- 定休日:第2木曜日
- TEL:045-341-4823
- 〒231-0063
神奈川県横浜市中区花咲町1丁目19-3
セルアージュ横濱桜木町ヴァルール101号室
松山漢方相談薬局 鶴見店
- 営業時間:10:00〜20:00
- 定休日:第2木曜日
- TEL:045-718-6801
- 住所:〒230-0062
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2-2
鶴見フーガII 3階

















